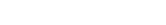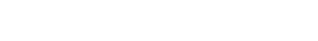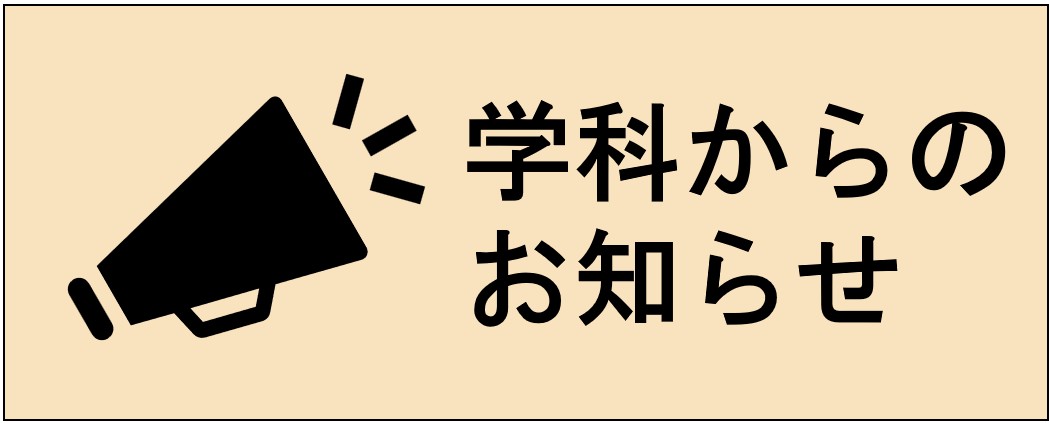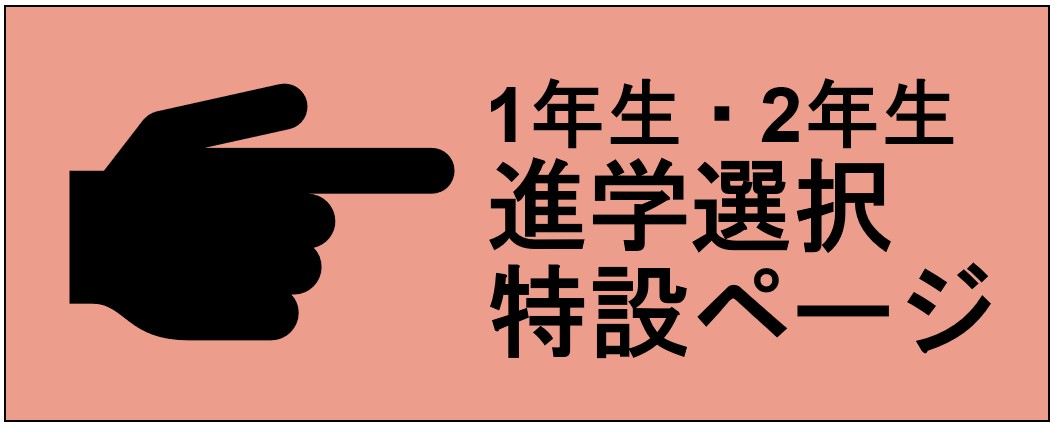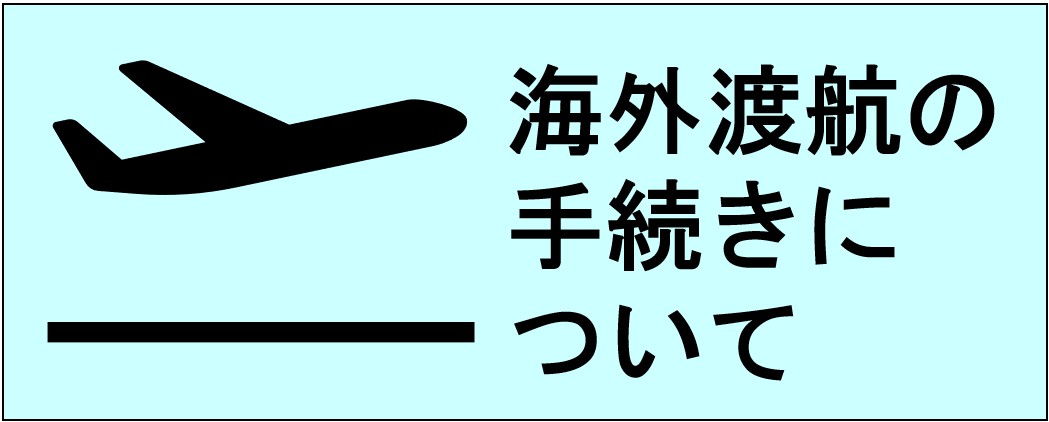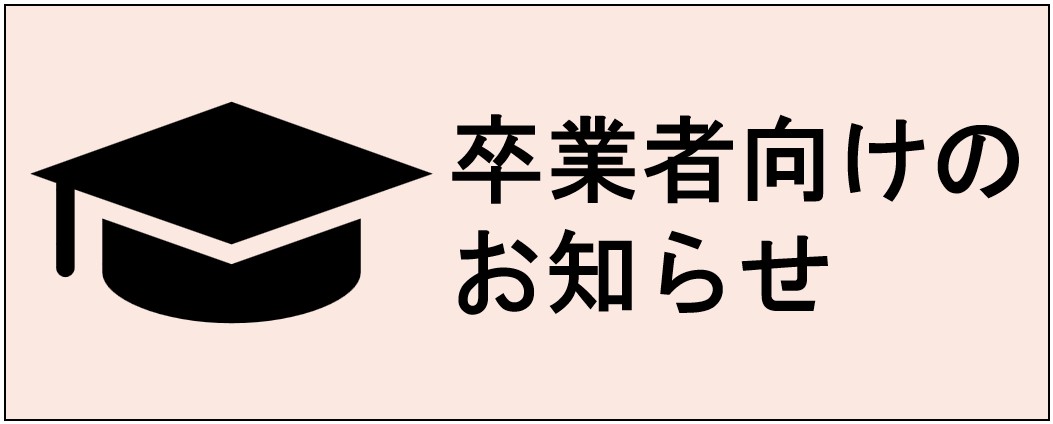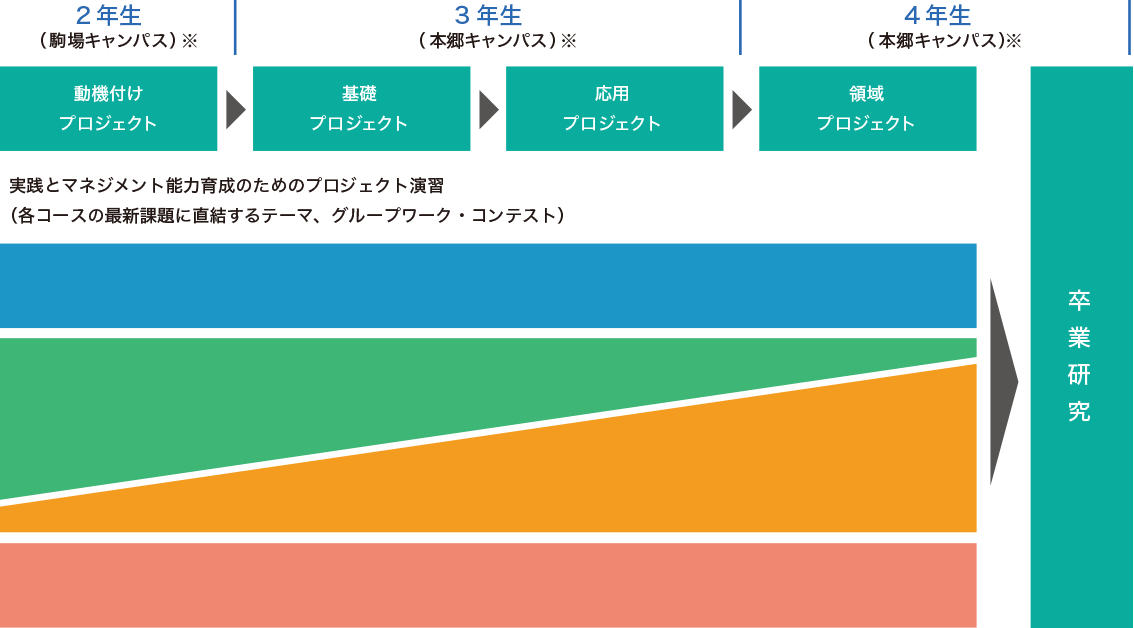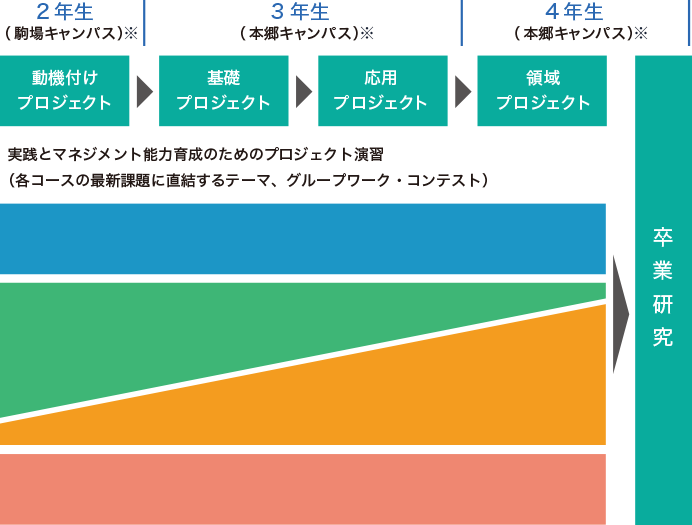システム創成学科のカリキュラムの特徴
問題の解析から問題の解決へ
⾼度にソフト化、システム化が進⾏する現代社会において、知識の伝達を中⼼とした従来型の産業基盤は過去のものとなり、設計、開発、研究に加えて、企画、教育、⾏政、プロデュース、コンサルティング等、⼯学部を卒業する学⽣の活躍の場は広がっています。 同時に、基礎⼯学に関する解析的能⼒に加え、論理的、システム的な思考⼒、統合⼒、リーダーシップ、コーディネーションといった能⼒が期待されています。 このような新しい社会状況に柔軟に対応できる⼈材とは「社会は何を必要としているのか」「そのために何を作るのか」「どのようにデザインし機能させるのか」という⾼い視点で考察、提案のできる⼈材です。 システム創成学科は、「問題」の設定と「解決」ができる⼈材の養成を⾏っています。
※一部例外があることがあります。また、プロジェクト系の授業では、スポット的にその他のキャンパスで実施することもあります。
汎⼯学技術と社会、環境とエネルギー、経済や安全といった、⼯学とその境界領域における技術、⼈間社会の課題を、学科(3コース)共通 の汎⼯学講義として設定し、「新しい⼯学」の基本理念を習得します。
技術・社会・環境・エネルギーなど⼯学とその境界領域における技術的・社会的課題を、学科共通の汎⼯学講義として設定し、「新しい⼯学」の基本理念を学習します。
- コース共通
- システム創成学基礎
- 環境・エネルギー概論
- 社会のための技術
- 設計学基礎
- 安全学基礎
- 経済学基礎
- など
基礎⼯学&基礎スキル「プラクティス」を重視し、演習や応⽤的な課題、マルチメディアの応⽤を通じて⼯学⼿法のKnow-Howを習得します。
プラクティスを重視し、演習や応⽤的な課題を通して⼯学⼿法の Know-How を習得します。
- 講義と演習
- 数理・情報⼯学系
- ⼒学系
- プログラミング等
プロジェクト演習グループ単位で⾏う研究の発表や討論を通して、実践的な応⽤⼒、課題探求⼒を習得します。 システム創成学科のカリキュラムの中⼼であり、全学期に設定されています。
応⽤プロジェクト 基礎プロジェクト 動機付けプロジェクト
グループ単位で⾏う研究発表や討論を通して、実践的な応⽤⼒、課題探求⼒を習得します。 システム創成学科のカリキュラムの中⼼であり、全学期に設定されています。
- 各教員のユニークな課題
- GW(+TA等のサポート)
- ⾝近な問題を考える 基礎的な設計・製作・調査 現実問題へのアプローチ
- 基礎⼯学&スキルの確認
領域⼯学各コースの専⾨性に応じた講義を⾏うとともに、プロジェクトおよび卒業研究に必要な専⾨知識を深め、 総合的な技術⼒、実践⼒、研究⼒を習得します。
各コースの専⾨性に応じた講義を⾏い、プロジェクトや卒業研究に必要な専⾨知識を深めます。各コースの領域工学科目の一例は以下の通りです。
Aコース(E&E)
環境・エネルギーシステム
- 電磁エネルギー科学
- 核融合エネルギー⼯学
- 海洋開発⼯学
- 環境調和論
- 環境・エネルギーの化学
Bコース(SDM)
システムデザイン&マネジメント
- レジリエンスコロキウム
- データ指向モデリング
- 先端コンピューティング
- ⾦融市場の数理と情報
- マルチエージェントシステム
- ⽣命知コンピューティング
Cコース(PSI)
知能社会システム
- 技術プロジェクトマネジメント
- ライフサイクル⼯学
- ビジネス⼊⾨
- 特許法
卒業研究 領域プロジェクト 卒業論⽂
80名弱の教員が提⽰する様々な研究テーマと充実した指導体制
※配属は、PSIコースは3年生の2月中に、 E&Eコースは4年生の4月中に、SDMコースは4年生の5月中に行います。
最近のテーマはこちらからご覧ください。